本日(3/22)、無事、卒業式を終えました。
本校の卒業式の特徴として、体育館中央の演台で、児童が夢や希望を言ってから卒業証書を受け取っています。今まで何回か練習はしていたのですが、今日は一段と凛々しく、力のこもった声で発表ができていました。私自身、気持ちが高ぶってしまったらどうしようという思いがあったのですが、子どもたちの引き締まった顔を見たら、すがすがしい気持ちになりました。
校長式辞では、
・「まごころ」の精神が、随分定着したこと。先日の「6年生を送る会」では、子ども・先生・保護者のまごころがつながり「和」になったと感じたこと。
・本校はコミュニティスクールで、地域のボランティアの方にたくさん支えられていること。そのお礼は、この味生地域を大好きになること。大人になったときに、地域で子どもたちのためになる活動を行うこと。これが恩をつなげていくことになるということ。
という話をしました。
PTA会長様からは、「おかげさま」の気持ちを大切にというお話をいただきました。卒業生の「旅立ちの言葉」では、代表児童の挨拶と合唱がありました。大変、立派な態度で卒業に際しての決意が伝わってきました。卒業生保護者の代表の方からは、教職員や地域の方々、在校生に丁寧なお礼の言葉をいただきました。教室に帰ってからの学級活動では、担任が熱い思いを語っていました。
5年生と教職員に見送られた後、正門前に設置している「卒業式」の看板横で記念撮影をしようと子どもと保護者の行列ができていました。今年度は、映えスポットとして垂れ幕を用意していましたので、そちらも人気でした。



本日、令和5年度 第41回 味生第二小学校卒業式が行われました。
子どもたちの心のこもった言葉と美しい歌声が響いた体育館。
5年生、教職員、保護者、ご来賓の方に見守られた心温まる卒業式でした。





保護者の皆様、本日は誠におめでとうございました。
来賓の皆様、味生二っ子の門出を見守っていただき、本当にありがとうございました。
卒業生の皆さん、中学生になっても「まごころ」を忘れず、自分らしく羽ばたいてください。
教職員一同、いつまでも応援しています。
ひばり
ひばり組では、23日に卒業する6年生とのお別れ会を行いました。総合企画は5年生、司会を2年生、はじめの言葉を1年生、終わりの言葉を4年生が担当。みんなで「だるまさんの1日」や「ハンカチ落とし」をして楽しみました。どのゲームも盛り上がり、6年生との楽しい時間を過ごすことができました。6年生の「みんなでソーラン節を踊りたい。」という希望で全員で踊り、盛り上がりました。
最後はプレゼントタイム。3年生が代表して、手作りの「記念アルバム」を心の込もったメッセージを添えて渡しました。6年生は、一生懸命に会を進めてくれた下級生へ「メッセージ付き写真立て」と各教室に「ひばりんたちのイラスト付きの旗」を贈りました。6年生との最後の時間を大切に過ごし、心温まるお別れ会になりました。




1年生は津田公園に遠足に行きました。初めての遠足でしたが、安全に気を付けて歩くことができました。津田公園には長い滑り台があり、大人気でした。おにごっこをしたり遊具遊びをしたりひなたぼっこをしたり、思いっきり遊びました。



たくさん遊んだあとは、楽しみにしていたお弁当を食べました。「おいしいね。」と言い合いながら笑顔で完食しました。お弁当を食べたあとには、おやつも楽しみました。



遊び方の約束をきちんと守り、楽しい思い出を作ることができました。
4年生は、総合的な学習の時間に、地域のお年寄りの方へメッセージカードを作りました。
子どもたちは、受け取るお年寄りの方の笑顔を思い浮かべながら、心を込めて丁寧に作っていました。
折り紙の飾りを付けたり、イラストを描いたりして、明るく楽しいカードが完成!
春の俳句も添えて、春らしいメッセージカードができました。お年寄りの方にもうすぐ届けます!
子どもたちの思いが伝わり、ほっこりした気持ちになっていただけたら嬉しいです♪

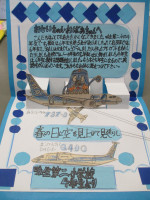
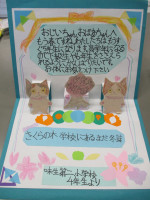


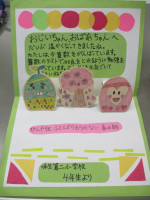
先日はお別れ遠足がありました。5年生は見学を兼ねていたので3月12日(火)に、他の学年は雨天のため延期し、13日(水)に実施しました。12日も雨が降ったのは登校中と帰校中のみで、遠足自体には影響がありませんでした。13日は見事に晴天となり、思いっきり活動ができました。
行先は、
1年生:津田公園、2年生:大可賀公園、3年生:松山総合公園、4年生:中須賀公園、5年生:愛媛新聞社・愛媛CATV・城山公園、6年生:校内遠足 です。






6年生は、卒業プロジェクトが活躍し、学校へのお礼として奉仕活動を行った後、思い出作りとしてレクリエーションを楽しんだり、お気に入りの場所でお弁当を食べたりしました。
6年生は、本日(3/14)卒業式の総練習を行いました。本校の特徴として、将来の夢(誓い)を述べてから卒業証書を受け取ります。子どもたちの熱い思いを目の前で聞くと、私も胸が熱くなりました。当日は、子どもの表情がみなさんにも見られるように、表情を撮影した映像をステージのスクリーンに映す予定です。
「旅立ちの言葉」では、代表者の言葉や卒業生による合唱があり、じーんとくるものがありました。卒業生の保護者の皆様、お子様が立派に卒業する姿をご覧になっていただけたらと思います。当日はハンカチをお忘れなく。
各教科で、学年のまとめを進めています。
この一年間、楽しみながらたくさんのことを学んできました。
友達と関わりながら学習することで、大きく成長しました。




ひばり
今日は、ひばり組のお別れ遠足でした。心配していた天気にも恵まれ、バスに乗って新玉児童館・新玉公園に行きました。新玉児童館では、子どもたちはいろいろなおもちゃで仲良く遊びました。新玉公園では、5年生が企画した遊びを全員でしたり、遊具を使って過ごしたりして交流を深めました。
お昼は、お楽しみのお弁当。大きな輪になってみんなで食べるお弁当は、おいしさも倍増です。
もうすぐ卒業する6年生と記念撮影をして、とても素敵な思い出ができました。




今までお世話になった6年生のために、一生懸命出し物の練習をしてきました。本番では、大きな声ではきはきとお礼の気持ちを伝えることができました。



終えてからは、「笑ってくれていた!」「かわいいって言われた!」「褒めてもらえた!」とうれしそうに話していました。6年生とのお別れは寂しいですが、しっかりと感謝を伝えられる機会となりました。あと少しの時間を大切に過ごせるといいですね。